「占い師になったのは良いけど、税金はどうなるの?」と不安になる方も多いと思います。
もちろん、多く稼いだら納税しなければなりません。ですが、なるべくなら節税はしたいですよね?
そこで、本日は、占い師の節税対策について考えてみます。
(カウンセラーやヒーラーさんなども同じです。)
こちらの記事は、専門家のアドバイスを参考に書いてます。
ただし、当サイトは税の専門サイトではありません。
あくまで「参考」として捉え、実行する際は税理士にご相談ください。
占い師が節税するために知っておくべきこと

占い師の節税には、以下の点が重要になります。
- 扶養されている人は、収入を130万円以内に収める
- 業務日誌をつける
- 物品購入の領収書をとっておく
- 家賃や電気代は経費で落とせる(自宅勤務の場合)
- 占いに必要なものは経費で落とせる
…一つ一つ説明してゆきますね。
1.扶養されている人は、収入を「130万円以内」に収めるべき
占い師の開業で「扶養」や「社会保険」はどうなる?で書きましたが、
簡単に言うと、収入が130万円を超えてしまうと、健康保険では「扶養の適用外」になってしまいます。
ですので、扶養から外れたくない方は、収入を130万円以内に収める必要が出て来ます。
- 税法上の扶養:所得金額で判定します。
- 健康保険上の扶養:収入金額で判定します。
扶養から外れると、税金や保険料が増える可能性があります。
扶養者の加入している健康保険組合や税理士に相談し、確認しておきましょう。
2.業務日誌をつける
収入が増えてくると、いずれ「確定申告」をしなければならなくなります。
もちろん経費も申告する必要があります。
その際、業務日誌があるとないでは違いが出てきます。
たとえば、占いのリサーチで原宿に出張したとしても、税務官から見て「それが本当かどうか」はわかりません。
そんな時、業務日誌にその「出張の詳細」が書かれていれば、その正当性がわかるわけです。
業務日誌は、日々の業務内容や収入、支出などを記録するものです。
確定申告の際に、経費の信憑性を高める上で役立ちます。

業務日誌は法律で義務付けられているわけではありませんが、つけておくと安心です。
3.物品購入の領収書をとっておく
たとえば、占いの本を買った場合、当然、経費で落としたいですよね?
それだけでなく「タロットカード」「占い師衣装」なども、経費としたいです。
ただし、それには領収書が必要です。
必要経費にしたい支出は、必ず領収書を取っておきましょう。
経費として認められるのは、事業に直接関係する支出のみです。
領収書は、経費として計上する際に必要な証拠書類となります。
忘れずに保管しておきましょう。
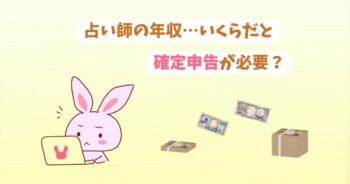
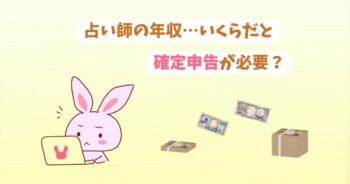
4.家賃や電気代は経費で落とせる(自宅勤務の場合)
占い師の中には、自宅でネット占いを開業している人も多いと思います。
そんな場合、家賃や電気代なども経費で落とせます。
しかし、仕事場だけでなく住居としても利用している場合、100%の経費にはなりません。
たとえば、仕事利用で3割ほど使っているのなら、30%の経費にする事は可能です。
その場合、家賃が6万円なら「1.8万円」を経費として落とすことができます。



これを「按分(あんぶん)」と言います。
自宅兼事務所の場合、家賃や電気代を按分して経費にすることができます。
ただし、税務署の判断によっては、按分比率が認められない場合があります。
5.仕事で使った経費は申告する
税金は所得に対してかかってきます。
所得とは「収入-経費」です。
つまり、正当な経費があれば、それはイコール節税になるわけです。
仕事に関連した支出であれば、経費として申告しましょう。
経費の例
- 占いに必要な道具(タロットカード、書籍など)
- 通信費
- 交通費
- 広告宣伝費
- セミナー参加費
- 税理士への相談料
占いの仕事で使ったものはないか?今一度、支出をチェックしてみましょう。
経費として認められる範囲は、税法で定められています。
事業に直接関係のないプライベートな支出は、経費として認められません。
6.青色申告を検討する
青色申告は、白色申告に比べて、以下のような節税メリットがあります。
可能であれば青色申告を検討しましょう。
- 青色申告特別控除
- 専従者給与
- 赤字の繰り越し
青色申告をするには、事前に税務署に申請が必要です。
複式簿記での記帳が必要になりますが、会計ソフトなどを活用すれば比較的簡単に行えます。
まとめ
今回は、占い師の節税対策!知っておきたいポイントを解説しました。
占い師として活動する上で、税金の知識は欠かせません。
節税をすることで、手元に残るお金を増やすことができます。
この記事を参考に、ご自身の状況に合った節税対策を検討してみてくださいね。
こちらの記事は、専門家のアドバイスを参考に書いてます。
ただし、当サイトは税の専門サイトではありません。
あくまで「参考」として捉え、実行する際は税理士にご相談ください。

